「香典の金額についてどれだけ包むべきか迷っている」という人は多いと思います。
また、予期せぬ出来事に直面し、香典やお花代の対応に不安を感じている人へのアドバイスも行います。
誤った方法で香典やお花代を提供すると、知らず知らずに遺族を不快にさせてしまう恐れがあります。
この記事では、香典やお花代の適切な金額の目安、封筒の書き方、遅れた場合の対応方法などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。
香典やお花代の相場に関するガイド
最近の傾向として、家族葬を選ぶ方が増えており、香典やお花代を辞退されることが多いです。
香典やお花代の相場は、その地域や故人との関係性によって変わるため、葬儀への参列前に金額を確認することが重要です。
一般的な相場は以下の通りです:
- 親:5万円〜10万円
- 兄弟・姉妹:3万円〜5万円
- 祖父母:1万円〜3万円
- その他の親戚:1万円〜3万円
- 友人・知人・近隣の方々:3千円〜1万円
- 職場の同僚:3千円〜1万円
※これらは、故人との関係度合いに基づいた相場です。
香典は故人へのお供えや遺族への金銭的支援を意図しています。
対して、お花代は供花の費用や、訃報を遅れて知った際に香典の代わりに用いることがあり、その意味合いには差があります。
故人と同居していた家族や喪主の場合は、香典やお花代の用意は必要ありません。
遅れて訃報を知った際の香典やお花代の金額目安
四十九日を過ぎて故人の訃報を知った場合、弔意を表すためにお花代を贈ることが適しています。
遺族がお花代の提供を辞退する場合、弔意だけを伝えるのが適切です。
この場合、香典の代わりにお花代を贈る際の相場を以下に示します。
相場のガイドライン:
- 親や兄弟:5万円~20万円
- 祖父母:1万円~5万円
- その他の親族:1万円~3万円
- 職場の人、友人、近所の方:3千円~5千円 ※この相場は故人との関係に応じて異なります。
遺族に負担をかけないため、適切な金額を心がけましょう。
通常、香典とは異なり供花の代わりとしてお花代を贈る場合、一般的には1万5千円から2万円が標準とされています。
遅れた場合のお花代の封筒への記入方法
お花代を封筒に入れる際の正しい書き方について不安に思うことがあるかもしれませんが、こちらでその方法を詳しくご説明します。
封筒への記入方法
一般的な白い封筒に水引がなくてもお花代を入れることは問題ありません。
白い封筒を使用する場合、表面の上部中央に「御花代」または「お花代」と記入し、下部中央に自分のフルネームを書きます。
裏面には自宅住所、フルネーム、包む金額を書くのが一般的です。
不祝儀袋を選ぶ際、「お花代」や「御花代」と印刷されたものが適しています。
不祝儀袋に添えられた札を使用する場合、札の下部に自分のフルネームを記入します。
また、「お花料」や「御花料」と記された札もありますが、これらは主にキリスト教式の葬儀で使われることが一般的で、宗教に応じて選ぶと良いでしょう。
訃報を遅れて知った時の香典やお花代の渡し方
四十九日を過ぎてから故人の訃報を知る場合があります。
訃報を聞いた後、できるだけ早く香典やお花代を渡すのが好ましいですが、遺族が辞退を希望する場合は、強引に渡す必要はありません。
香典やお花代を渡す際には、封筒の表面上部中央に「お花代」と記入し、下部中央には自分のフルネームを記すのが一般的です。
四十九日までに渡す場合、薄墨の使用が望ましいです。
お返し不要の場合の書き方
遺族への負担を考慮し、お返し不要を希望する場合もあるでしょう。
この意向を適切に伝えるためには、マナーを守ることが重要です。
香典袋への記入
お返し不要の旨は、香典袋に直接「お返しは辞退させていただきます」と記入することが可能です。
裏面や、中袋がある場合は住所の隣に同じ文言を添えます。
一筆箋の利用
簡潔な一筆箋を使って、辞退の旨を書く方法もあります。
宛名、挨拶文、結びの言葉、署名を順に記述します。
一筆箋は縦書きが望ましいです。
書く際には忌み言葉に注意し、礼儀正しさを心がけてください。
受付での伝え方
香典を渡す際、受付でお返しを受け取ることがあるため、辞退の意向を受付で伝えることもできます。
受付担当者は通常遺族ではないことが多いため、曖昧な表現ではなく、「お返しは辞退させていただきます」と明確に伝えましょう。
受付でお返しの辞退を伝えた後、香典の封筒の裏面や一筆箋を併用すると、遺族の方に伝わりやすくなります。
お金の収め方
お金を包む際、封筒や袋の表面ではなく、お金は裏側にして人物が下向きになるようにしましょう。
お札には、人物が描かれている面(表面)と、人物が描かれていない面(裏面)があります。
そして、人物が描かれている面を上に、人物が描かれていない面を下にしましょう。
香典を包むお札の向きは「裏側・下側」にすることで、悲しみや哀悼の気持ちを表現します。
お札は、しわくちゃでない新札ではなく、適度に使用感のある状態の綺麗なお金を使用しましょう。
新札しかない場合でも、二つ折りにして中央で折り込み線を入れてから包むことが適切です。
なお、新札を使わない理由は、故人が亡くなることを予想してお金を用意していたと感じさせないためです。間違った収め方は失礼とされているため、お札の向きや状態には十分に注意しましょう。
他の贈り物のエチケット
葬儀に出席できない場合、香典やお花代を贈ることが一般的です。
贈り物の際にも、特定のエチケットが存在しますので、参考にしてください。
現金書留を利用する
葬儀に参加できない場合や遠方にいる場合、香典を郵送することが選択肢となります。
郵送する際には、現金書留を活用することが一般的です。
現金を送る場合、郵便法第17条に基づき、現金書留の専用封筒を使用します。
直接現金を専用封筒に入れるのではなく、不祝儀袋や封筒に包んでから、それを現金書留の専用封筒に入れましょう。
葬儀会場で香典を受け付けている場合、専用封筒に「〇〇斎場気付○○家○○様」と書いて送ることができます。
しかし、会場で受け取りが難しい場合や葬儀までの時間が制約されている場合は、喪主の自宅へ香典を郵送することを検討しましょう。
自宅へ送る際には、遺族の都合が合う日を確認して送ることをお勧めします。
水引の選び方
贈り物に不祝儀袋を使用する際の、選ぶ際のポイントについてお伝えします。
不祝儀袋には、贈る金額によって選ぶべき水引の種類がありますので、適切な水引を選びましょう。
1万円程度の場合:印刷された水引
3万円までの場合:白黒の水引
3万円以上の場合:双銀の水引
不祝儀袋を購入する際には、水引の種類にも注意して選ぶことが大切です。
日数が経過した際の香典やお花代のまとめ
今回、遅れて香典やお花代を贈る際の方法についてご紹介しました。
贈る金額は故人との関係によって異なるため、事前に確認し、相場に合った金額を包むように心がけましょう。
また、ここで示したのは一般的な相場ですので、地域やご家庭の習慣によって異なる場合もあるでしょう。
その他のエチケットも参考にしながら、香典やお花代を贈る際には遺族の気持ちを尊重し、自分の気持ちを伝えるように心がけましょう。


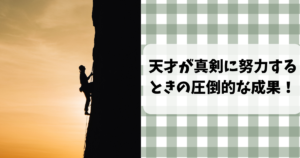

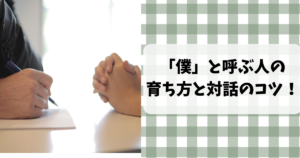





コメント