墓地の入口や道端でお地蔵さんを見かけた経験は、多くの人にあるかもしれません。
お地蔵さんは仏像の一種で、お寺にある壮大な仏像とは異なり、よく屋外に設置されています。
これにより、私たちの日常生活にとても身近な存在になっています。
しかし、皆さんは「お地蔵さんには手を合わせてはいけない」という言い伝えを聞いたことがありますか?
実際には、全てのお地蔵さんがこの規則に当てはまるわけではないのです。
外見が似ているお地蔵さんでも、実は様々な種類があり、手を合わせてもいいものとそうではないものがあるんです。
では、どのお地蔵さんに手を合わせるべきではないのでしょうか?
この点について、今回はあまり知られていない「お地蔵さん」に焦点を当てて解説します。
お地蔵さんには手を合わせてはいけないというのは本当?
どんなお地蔵さんに手を合わせるべきではないのでしょうか?
それは、「管理者が不明なお地蔵さん」です。
街中でたまに目にするかもしれません。
ひとりぼっちで置かれた小さな祠の中や、道の脇で静かに立つお地蔵さんのことを指します。
これらのお地蔵さんは、亡くなった方々の鎮魂のために設置されていることが多いですが、そこに悪霊が集まるとされています。
そのため、そういったお地蔵さんには手を合わせない方が良いと言われています。
このタイプのお地蔵さんを見かけた時は、基本的に無視するのが推奨されています。
ただし、お寺が管理しているお地蔵さんなら問題ありませんので、安心してお参りしましょう。
お地蔵さんに手を合わせてはいけないのはどうして?
お地蔵さんがなぜ屋外、特に道端によく設置されているのか、その背景にはどんな理由があるのでしょうか?
この現象は、お地蔵さんの特性と、日本に古くから伝わる「道祖神」信仰が組み合わさった結果として理解されます。
お地蔵さんの意味
お地蔵さんは、仏教における地蔵菩薩として知られる仏様の一つです。
仏教では、仏様が多様な形で存在し、それらは大まかに5つのグループに分類されることがあります。
①如来(にょらい)は、最も高い悟りの境地に達した存在。本来、「仏」という称号は如来にのみ与えられる。
②菩薩(ぼさつ)は、如来になる過程の修行者であり、一般の人々と共に歩み、指導を行う。
③明王(みょうおう)は、如来の別の姿ともされ、怒りの表情で悪を退治し、仏法を守る役割を担う。
④天部(てんぶ)は、インドの古い神々が仏教に護法神として取り入れられた存在で、帝釈天や大黒天、毘沙門天などがこれに該当する。
⑤垂迹(すいじゃく)は、如来や菩薩が人々を救うために一時的に異なる姿をとって現れることを指す。
お地蔵さんは、民衆と共に歩むとされる菩薩です。
この菩薩は、人間界のみならず地獄の奥深くまで行き、人々の苦悩を代わりに負う「代受苦(だいじゅく)」としての役割を果たしています。
地蔵菩薩の日本における役割
平安時代、日本で浄土信仰が拡がると、「極楽浄土へ行けなければ地獄へ落ちる」という観念が広まりました。
貴族達は寺院の建設や仏像の造立を通じて徳を積み、極楽への途を求めました。
その一方で、貧しい民衆は、地獄の苦しみから救いを求めて地蔵菩薩に祈りました。
彼らに親しまれる道端などに、苦難を代わりに受けてくれるありがたいお地蔵さんが各地に設置されるようになったのです。
お地蔵さんが赤いよだれかけをつけている理由は何でしょうか?
赤色は魔除けの効果があるとされ、また子どもの健康な成長を祈る色としても知られています。
伝承によれば、親より先に亡くなった子どもは「賽の河原」へ行くとされています。
ここで子どもたちは石を積んで成仏を目指しますが、鬼が現れて石を崩すと言われています。
昔の日本では、不衛生な環境や栄養不足により、子どもの死亡率が高かったことがあります。
親より早く死ぬことが罪であるかのように思われがちですが、それは子どもたちの責任ではありません。
そうした不憫な子どもたちを守り、救うのがお地蔵さんの役割です。子どもたちに近しい存在として、子どものような姿に変化し、よだれかけをするようになったとされています。
関西地方では、子どもの幸福を願う「地蔵盆」という行事が毎年8月23日と24日に行われています。
仏教における地蔵菩薩
地蔵菩薩に関する仏教の教えについて見てみましょう。
仏教においては、「生きるということが本質的に苦しい」という考えが根底にあります。
人間は六道輪廻(ろくどうりんね)、つまり生と死を繰り返す苦しいサイクルの中に生きていますが、この連続から脱することができるのは如来だけとされています。
輪廻とは、絶えず回る車輪のように、「永遠に続く反復」を象徴しています。
人々は、以下の6つの異なる世界で生まれ変わります。
どの世界へ生まれ変わるかは、この世での行動によって決定されます。
その中の一つに、苦悩が絶えない世界である地獄道(じごくどう)があります。
この世で罪を犯した者が転生する世界には、非常に多くの苦しみが存在します。次の生まれ変わりまでの間、彼らは絶え間ない苦痛を経験することになりますが、その期間は非常に長いです。
罪の重さや種類に応じて、軽度の地獄から重度の地獄まで、合計8種類の地獄が存在するとされています。最も軽い地獄でさえ、その寿命は1兆6千億年にも及ぶと言われています。
自己中心的で貪欲な人々、自分だけの楽しみや幸せを追求する人々が転生する世界には、厳しい苦しみが待っています。彼らは飢えと渇きに悩まされますが、食べ物や飲み物が目の前にあっても、それを口にするとすぐに炎に変わり消えてしまいます。
その結果、彼らは最終的に骨と皮だけの状態になりながらも、なかなか死ぬことができないという過酷な状況に置かれるのです。
他人の幸せを妬んだり、他人の不幸を楽しむような人たちが転生する世界は、自然界のように厳しい生存競争の場です。この世界では、動物や鳥、虫のように、弱いものが強いものに支配されます。
牛や馬のように重労働に従事させられることもあります。また、自分よりも強く、大きな存在に襲われるかもしれないという常時の不安に怯え、苦しむことになります。
私たちが現在生きているこの世界は、苦しみや困難が存在する一方で、幸福や楽しみも経験できる場所です。六道の中では、この世界だけが仏教の教えを学ぶ機会を持ち、それによって六道輪廻のサイクルから脱出する可能性があるとされています。
六道のうちで最も楽しいとされる世界は、神通力を使え、多くの快楽に溢れています。長寿を楽しむことができるものの、最終的には寿命が尽き、死後には六道のいずれかに再び転生します。この世界は苦しみから完全に解放されている「極楽浄土」とは異なり、一時的な快楽に満ちているに過ぎません。
釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)の死後、弥勒菩薩が成仏するまでの間、新たな如来(悟りを開いた者・仏)が現れないとされています。
この期間は56億7千万年にも及ぶと言われていますが、これは実際の時間ではなく、「永遠」を象徴するために使われた誇張された数字です。
この如来が現れない時代において、人々の救済を担うのが地蔵菩薩です。
地蔵菩薩は、本来如来になれる資格がありながら、「六道すべての存在を救うまで成仏しない」という強い誓いを立てています。
そのため、地獄のような苦しい場所にも足を運び、人々の苦難を代わりに受けています。
お地蔵さんは非常に重要な役割を持つ尊い存在であり、手を合わせる際には注意が必要です。
六道それぞれに分身を送るとされ、6体セットで製作されるお地蔵さんもあります。
道祖神との関係
お地蔵さんにまつわる話に混乱をもたらす要素の一つが「道祖神」という存在です。
道祖神とは、古来、日本の村の境界や峠、交差点などの重要な場所に設置される魔除けのことを指します。
この習慣は、災害や悪霊、病気など外部からの不幸を防ぐ目的で行われていました。初めは単なる棒や石が使われていましたが、やがて石碑や石像へと変化していきました。
『日本書紀』では、イザナギが黄泉の国の境界に岐神を設置して穢れを防いだと記されています。
また、道祖神は外部からの守護神であると同時に、外へ出ていく人々を守る役割も担っていました。
そうして、道や旅人の安全を守る神としての性質を持つようになりました。
一部のお地蔵さんは道祖神の特性を持っています。
多くの人がお墓の入り口に立つお地蔵さんを目にしますが、これらはこの世とあの世の境界に置かれ、道祖神としての役割を果たしています。
さらに、何もない道端に突然置かれているお地蔵さんは、旅の安全を祈る対象であり、途中で亡くなった人々を供養する役目も持っています。
しかし、時間が経過し供養されるべき人が不明になったお地蔵さんの周りには、悪霊が集まることもあります。
そのため、お地蔵さんと道祖神との区別がつかない場合は、手を合わせることを避けるべきです。
お地蔵さん手を合わせてはいけない訳
道端にあるお地蔵さんには手を合わせることは控えめにされがちですが、お寺できちんと管理されているお地蔵さんには、敬意を持ってお参りするのが適切です。
お地蔵さんは、苦しみを引き受けるだけでなく、さまざまな願い事を叶える力を持っているとされています。
健康や長寿、豊かな収穫、交通の安全、子宝や安産、水子の供養、子どもの守護などがその例です。
特定のお地蔵さんは特定の願いに強い力を発揮するため、自身の願いに合ったお地蔵さんを訪れることが重要です。
お地蔵さんの起源は、インドのバラモン教の大地の女神「プリティヴィー」にあります。この女神は豊かさや財をもたらし、病を癒す力を持つとされています。仏教において、地蔵菩薩として取り入れられた際、この女神の特性を引き継ぎました。
お地蔵さんと餓鬼
お地蔵さんと餓鬼(がき)との繋がりについて、その母性的な側面をお話しします。
一般には見えないものの、実はお地蔵さんの足元には餓鬼道への入り口があるとされています。
餓鬼たちは、普通の食べ物や飲み物を口にすると炎となり消えてしまうため、常に飢えや渇きに苦しんでいます。
しかし、お地蔵さんに捧げられたお水は、餓鬼たちに届く唯一のもので、一時的にその苦しみを軽減します。
まるで母親の母乳以外受け付けない赤ちゃんのようです。
このお地蔵さんと餓鬼との関係は重要です。
ある家庭で間違えて祀られた手を合わせてはいけないお地蔵さんのために、家の中の飲み物が減るという現象が起きたと言われています。
霊感のある人に
お地蔵さんと餓鬼(がき)との繋がりについて、その母性的な側面をお話しします。
一般には見えないものの、実はお地蔵さんの足元には餓鬼道への入り口があるとされています。餓鬼たちは、普通の食べ物や飲み物を口にすると炎となり消えてしまうため、常に飢えや渇きに苦しんでいます。
しかし、お地蔵さんに捧げられたお水は、餓鬼たちに届く唯一のもので、一時的にその苦しみを軽減します。まるで母親の母乳以外受け付けない赤ちゃんのようです。
このお地蔵さんと餓鬼との関係は重要です。ある家庭で間違えて祀られた手を合わせてはいけないお地蔵さんのために、家の中の飲み物が減るという現象が起きたと言われています。霊感のある人に調べてもらった結果、家に餓鬼が棲みついていることが判明したそうです。
また、子どもに「どのお地蔵さんにも手を合わせるように」と教えることは可愛らしいものの、知らず知らずのうちに餓鬼を家に連れてくる可能性があります。したがって、大人は手を合わせるべきでないお地蔵さんの存在について子どもたちに教えることが必要です。
まとめ
実際に手を合わせるべきでないタイプのお地蔵さんが存在します。
道祖神の特性を持つお地蔵さんの中には、手を合わせることが推奨されないものが含まれています。
お地蔵さんは確かに母性的な側面を持つ一方で、潜在的な危険性も秘めています。
お地蔵さんは誰にでも救いの手を差し伸べる優しく強い仏様であるため、悪いものも彼らに助けを求めやすいという特徴があります。
日本のあちこちでお地蔵さんを見かけることはできますが、すべてのお地蔵さんに安易に手を合わせるべきではありません。お寺などで適切に管理されている、信頼できるお地蔵さんに手を合わせるのが望ましいです。


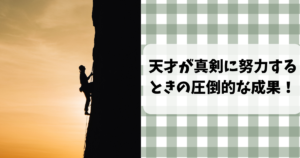

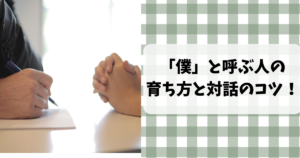





コメント